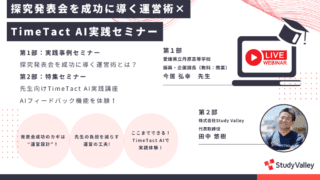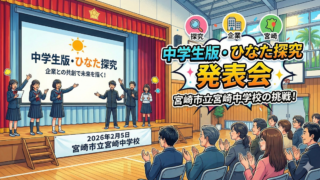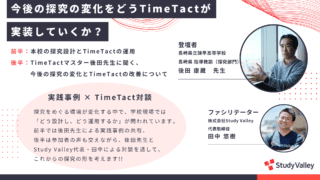探究学習で有名な海外高校の探究事例5選

海外にはどのような探究学習の実践例があるのでしょうか。
この記事では、アメリカ、イギリス、中国、インドネシア、そして世界を旅する高校の事例を紹介し、その特徴を解説します。
【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
探究学習とは?
そもそも探究学習とは、生徒が好奇心を原動力にして批判的思考力を活用し高めていく実践型の学習スタイルです。
探究学習がうまく機能しているとき、生徒は自ら問いを掲げたり解決策を考えたりします。その過程で主体性や好奇心、そして創造性を発揮し、伸ばすことができるといわれています。
しかし探究学習には厳密な定義やガイドラインはないので、これだけだとまるで哲学や職人技のように掴みどころがありませんね。
実際に「探究学習」を導入しようとしても、特に慣れないうちは「どういう授業が」探究学習にあたるのか、どうすれば普段の授業が探究学習に近づくのかがわかりにくいのではないでしょうか。

この記事では探究学習を積極的に取り入れている海外の学校を紹介します。
この記事を書いている2021年現在、どの国の教育現場でもパンデミックによる影響が生じていますが、探究学習に熱心に取り組んでいる学校は、先生の知恵や工夫によって日々新しい学習体験が作り出されています。
具体的な事例を知ることは、「探究学習像」をつかみたい教育者や保護者には特におすすめです。また、特徴的な海外事例に触れることは、すでに探究学習を実践している方にも新鮮な発見があるでしょう。
海外の事例を通して教育や学校の新たな可能性を発見し、今日からの教育実践に役立てていきましょう。
アメリカの公立校・ハイテックハイの「禁書プロジェクト」

最初にご紹介するのは、アメリカ・カリフォルニア州にある公立学校のネットワーク「HighTechHigh(以下、ハイテックハイ)」です。
ハイテックハイの特徴
ハイテックハイは16の学校から構成されており、幼稚園から高校生まで6,000人以上が学んでいます。
これらの学校に共通している基本的な考え方は「各々の個性を尊重しつつ、互いに良好な関係を築き、課題を共有できる学習環境を整える」というものです。
そんなハイテックハイの探究事例をご紹介します。
ハイテックハイの探究事例
ある年、生徒たちは過去に物議を醸して禁書となったことがある本をテーマに選び「禁書プロジェクト」を立ち上げました。

生徒は本の内容を理解するだけでなく、なぜその本が禁書になったのか、などを知るために、出版当時の時代や社会背景、検閲の役割などを探究していきました。
さらには、全米の高校生が参加する「禁書ウィーク」というイベントに参加し、出版や読書の自由についての議論と考察を深め、啓蒙活動に加わりました。
ハイテックハイは探究の成果発表や、そこで生徒たちが多くの人からフィードバックを得ることを重要視しています。そのためか公式サイトにはプロジェクト事例が多数掲載されています。よろしければご覧になってみてください。
ハイテックハイ公式サイト
Banned Books(禁書プロジェクト)
イギリスのトーマス・ディーコン校の自治活動

次にご紹介するのは、イギリス・ケンブリッジシャーにある私立一貫校の「Thomas Deacon Academy(トーマス・ディーコン・アカデミー。以下、TDA)」です。TDAには小2から高3までの生徒が通っています。
TDAの特徴
TDAの理念は「生徒一人ひとりが社会に積極的に貢献し、地球市民として「成長」するために必要な知識、技能、人格を身につけること」です。
TDAの探究事例

TDAでは、自治活動も探究学習のひとつの形です。
生徒たちは異なる学年が混ざったグループにわかれ、学内で変化を起こしたいと思うさまざまな課題について議論します。
議論の内容は、授業で教えている内容やクラブ活動や生徒のウェルビーイング(身体的・精神的・社会的に良好な状態にあることを意味する概念)など、あらゆることに及びます。
彼らの活動は議論にとどまりません。グループでまとめたことを学校改革担当の先生に報告し、さらなる学習と議論が必要な問題と、すぐに取り組める問題とに分け、問題解決へ向けて行動を開始します。
この取り組みには、学校の課題を、学生が自分ごととして捉え、意見を出し、互いに共有するという役割があります。
Thomas Deacon Academy公式サイト
異年齢の自治活動について(Facebook ページ)
中国のIB校・北京京西学校の「キャップストーン」

3校目として、中国・北京市にある「北京京西学校(英語表記:Western Academy of Beijing)」をご紹介します。
北京京西学校の特徴
北京京西学校は幼稚園から高校まであるインターナショナルスクールです。指導言語は英語で、生徒は主にアジアと英語圏の40カ国以上から集まっています。
北京京西学校では国際バカロレア(International Baccalaureat。以下、IB)を採用しています。IBというカリキュラムの目的はオープンマインドでバランスのとれた、知識と探究心のある学習者を育成することです。
北京京西学校の高等部カリキュラムは、生徒の興味や目標に関連したスキルを磨き、自主的な学習ができるように設計されています。
北京京西学校の探究事例

その独自の取り組みのひとつに「キャップストーン・プログラム」という、高2〜高3の生徒を対象とした選抜制の自主学習プログラムがあります。
キャップストーンに選ばれた生徒はメンターと協力して目標を設定し、達成に向けた手段を探究します。生徒は自作の学習計画を通して、テーマを深く掘り下げることができます。
たとえば、ある生徒は幼い頃から熱中してきた写真技術と情熱を活かして、学生でありながらフォトジャーナリズムの道を歩み始めています。生徒がキャリアにしてみたいことがあれば、学校のサポートの元、在学中から始められるのがこのプログラムの魅力です。
ほかにもプログラミング、ゲーミング、ダンスなど、クリエイティブで長期的なプロジェクトが展開されています。
生徒はキャップストーンの過程で専門家の協力を得たり、コミュニティの中でリーダーシップを発揮していきます。
そして最後には、各分野の専門家などからなる審査委員会の前で自分の学習成果を発表します。
北京京西学校公式サイト
キャップストーン・プログラムについて
世界を旅しながら学ぶ高校、TGSの「チェンジメーカー・カリキュラム」

4校目にご紹介するのはアメリカの私立高校の「THINK Global School(以下、TGS)」です。
TGSの特徴
TGSは高1から高3までの3年間で10カ国を旅しながら学ぶ「世界がキャンパス」の高校です(日本にも来たことがあります)。
TGSの生徒たちは「世界について」学ぶのではなく「世界の中で」学びます。各国現地で学ぶことで、多くの人が一生かけて経験する以上の歴史、地理、文化を高校生のうちに学ぶのです。
TGSの探究事例

現実社会のなかで探究する力や関連スキルを習得し、プロジェクト型学習を組み合わせながら、自分で自分の学習を主導していくTGSでの学びは「チェンジメーカー・カリキュラム」と名付けられています。
「チェンジメーカー・カリキュラム」では、メンターの指導のもと学期あたり3~5つのプロジェクトを進めていきます。
ある生徒は、このような問いを立てました。
仏教の哲学や自己と世界に対する考え方を深く理解するためにオリジナルの短編映画を制作するには、どうすればよいか?
この生徒は人の認知や行動、データ収集の基礎を学ぶほか、実際のドキュメンタリー映画監督にメンターになってもらい、写真や映像製作のスキルを学びました。
最終的には韓国の寺院で11日間の撮影旅行を実行。僧侶にインタビューし、寺院の生活や自然環境をカメラに収めました。その作品は現在、下記のYouTubeで視聴できます。
「Ecology of the Mind」生徒が実際につくった映像作品
THINK Global School公式サイト
チェンジメーカー・カリキュラムについて
バリ島・グリーンスクールの「グリーンストーン」

最後にインドネシア・バリ島にある私立一貫校「Green School(以下、グリーンスクール)」をご紹介します。
グリーンスクールの特徴
バリの熱帯林のなかにあるグリーンスクールは「壁がない学校」「エコな学校」として広く知られています。ここでは世界から集まった幼稚園から高3までの児童生徒が学んでいます。
グリーンスクールが奨励しているのは、地域に根ざし、環境を指針とし、自らの行動が子孫に与える影響を想定しながら動くことです。生徒は、主体的に学ぶことは教室の外でも、世界のどこでも必要になりうることだと理解するようになります。
グリーンスクールの探究事例

高校生は全員「グリーンストーン」という卒業プロジェクトを行います。グリーンストーンでは、生徒が自身の情熱や関心や問題意識に基づいて、プロジェクトを設計し実行します。最後には、その成果を13分間のTEDスタイルで発表します。
ある生徒は発酵食品に興味を持ち、その歴史や種類や加工方法、人体への効用を調べ、実際にたくさんの発酵食品を作ってその実践を発表しました。彼の発表の様子はこちら。
その他の生徒のプレゼンテーションも、公式サイトから動画で見ることができますよ。
世界の探究学習の共通点
ここまで探究学習を実践している世界各地の高校を5校ご紹介しましたが、どの事例にも共通しているパターンがあることにお気づきでしょうか。
どの高校の探究学習例においても、生徒はこのようなステップを踏んでいます。

日本の文部科学省の指導要領にある、探究のプロセスと本質は同じですよね。


そしてもう一つの共通点は、探究に取り組む子供たちが本当にすてきな顔をしていることです。
世界のどこであっても、探究学習が目指すところは同じです。
海外の例は、先進的な事例のように思われるかもしれません。しかし日本でも2022年から本格的に探究学習が始まります。
子供たちが活躍する未来では「探究学習」が世界の共通言語になっていくでしょう。
海外の事例からヒントを得て、子供たちがいきいきと取り組める探究学習が日本全国で行われることを期待しています。
【高校の探究担当の先生へ】
当メディアを運営する私たちStudy Valleyは「社会とつながる探究学習」を合言葉に、全国の高等学校様へ、探究スペシャリストによる探究支援と、社会とつながるICTツール「高校向け探究学習サービス『TimeTact』」を提供しています。
現在、探究に関する無料相談会を開催中です。探究へのICT活用や外部連携にご興味ある方、お気軽にご連絡下さい。ご予約はこちら(2024年3月現在、問い合わせが急増しております。ご希望の方はお早めにご連絡ください)。
【企業のCSR広報ご担当者様へ】
CSR広報活動の強い味方!
探究教育を通して、学校と繋がるさまざまなメリットを提供しています。
まずはお気軽に「教育CSRサービスページ」より資料をダウンロードください。
また無料相談も可能です。些細なご相談やご質問、お見積りなど、お気軽にご相談ください。
【この記事の監修者】

田中 悠樹|株式会社Study Valley代表
東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券→リクルートホールディングスに入社。同社にて様々な企業への投資を経験する中で、日本の未来を変えるためには子どもたちへの教育の拡充が重要であると考え、2020年に株式会社Study Valleyを創業。
2020年、経済産業省主催の教育プラットフォームSTEAM ライブラリーの技術開発を担当。
2024年、経済産業省が主催する「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」に委員として参加している。